
 |
 日本でもオンライン書店のサービスが続々と登場、インターネットを通じて本を販売・購入することがそうめずらしいことではなくなってきたが、ここにきて、よりオンライン化を進め、本そのものを電子ファイル化してインターネットで流通させようという動きが本格化しつつある。
日本でもオンライン書店のサービスが続々と登場、インターネットを通じて本を販売・購入することがそうめずらしいことではなくなってきたが、ここにきて、よりオンライン化を進め、本そのものを電子ファイル化してインターネットで流通させようという動きが本格化しつつある。
こういった“電子書籍”を扱う“電子書店”はこれまでも存在しており、「電子書店パピレス」はその老舗と言える。また、著作権の切れた古典作品などを無料で提供する「青空文庫」や、そのほかにもアマチュア作家による“ネット出版”の例は数え切れない。
それが今年に入り、講談社、角川書店、新潮社など8社が書籍を電子化してオンラインで販売する共同プロジェクト「電子文庫パブリ」を結成。このうちすでに徳間書店や光文社などがサービスを開始しているほか、9月にも講談社などがサービスインする予定だ。今までは、どちらかと言えばマイノリティのイメージがあったネット出版だが、これら大手出版社が乗り出すことでそれも変わってくる。また、印刷や物流を必要としないネット出版ということで、出版の位置づけも大きく変わる。
今回は、電子書店パピレスや青空文庫でも使われている電子書籍フォーマット「エキスパンドブック」を開発したほか、最近では電子文庫パブリに参加する講談社などへ電子出版システムを提供するなど、日本の電子書籍事業に深くコミットしてきたボイジャーの代表取締役・萩野正昭氏にお話をうかがった。同社の取り組みを振り返りながら、ネット出版時代における“本”のあり方について考えてみたい。
●「エキスパンドブック」で誰もが“本”を作れる手段を何をもって電子書籍とみなすかについてはいろいろな考え方があるが、それが本を模しているということが容易に想像できる点で、電子書籍の走りとも言えるのが「エキスパンドブック」だろう。
エキスパンドブックは、米国のニュ-メディア専門出版社であるVoyager社が開発した電子書籍フォーマット。1991年にAppleからPowerBookが発売されたのをきっかけに、ノートパソコンで本を読めるようにしようという電子書籍の開発プロジェクトがスタート、1992年にエキスパンドブックとして発表された。
エキスパンドブックでは、デジタルファイルという性質上、テキストの検索やハイパーリンクといった機能ももちろん可能だが、「ページをめくったり、しおりを付けたり、紙の本でできることはすべてできるようにした」というように、紙の本をコンピュータのディスプレイ上にそのまま再現しようという試みだった。当時のノートパソコンは本体も大きく、ディスプレイはモノクロで解像度も低かった。実験的な意味あいが強かったことは事実だが、「ノートパソコンで本を読むということがまったく絵空事ではなくて、近い将来、電子的な出版物があり得るという確信や期待を持てたことが大きかった」。米国では、マイケル・クライトンの「ジュラシックパ-ク」やウィリアム・ギブソンの「ニューロマンサー」などの作品がエキスパンドブック化され、FDによるパッケージとして発売。書店にも専用の陳列スタンドが置かれるなどして、約300タイトルがリリースされたという。
その後、ボイジャーの日本におけるベンチャーが立ち上がり、日本語にも対応。日本独自のタイトルがリリースされたほか、エキスパンドブック作成用のツールも提供された。前述の電子書店パピレスや青空文庫でのフォーマットとしても採用されているほか、現在までに数多くのアマチュア作家などが作品を発表するツールとして利用している。
これは、エキスパンドブックが、本を出版するという行為の対象範囲を拡大したことを意味する。それまで本を出版するということは、資金力のある一部の人間や出版社にしかできないことだった。これに対し、「誰にでも“本”が作れるということを言ったのがエキスパンドブックの世界」だったわけだ。
●電子書籍から紙という枠をはずした「T-Time」
 |
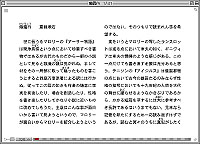 |
| T-Timeでは文字の大きさや段組みなど “本”のレイアウトが自由に変更可能だ |
1990年代半ば以降、日本でもインターネットが普及し、日本語コンテンツをインターネットで見る機会が多くなった。しかし、日本語のテキストの場合、WWWブラウザーによる表示はあまりにも読書をするというには耐えられないものだったという。
T-Timeは、専用フォーマットのファイルのほか、テキストファイルやHTMLファイルを読み込み、それらを縦書きで、きちんと行間のあるレイアウトで、読みやすいフォントで表示することができる。エキスパンドブックの「誰にでも本が作れる」ということに加えて、インターネットなどで提供されているデジタルファイルを「自分なりに本にして読める」というコンセプトが加わったわけだ。例えばそれまでは、ウェブサイト上の長文テキストを読む場合、いったんプリントアウトして紙の状態で読むのが普通だった。しかし、「そうではなくて、直接オンスクリーンで読むということが、我々の生活のニーズとしてあると思った」という。
さらにエキスパンドブックと異なるT-Timeの大きな特徴として挙げられるのが、読者側でレイアウトを変更できるという点だ。
これまで、本というものは「ある特定の形を持って、ある特定のレイアウトを持っているもの」と考えられていた。これは「編集者が編集して、彼ら専門家がいちばんいい形だと考える状態で読者のもとに届けるという出版のしきたり」があったから。しかし、これは、紙の本が「画一的なかたち」を持っていたから言えることであり、電子書籍を読むディスプレイには決まった大きさがない。また、コンピュータの環境だけでなく、歳をとっていて細かい字が読めないといった読者自身の差異もある。それならば、文字の大きさはもちろん、縦組み/横組みの変換も読者が自由に行なえるようにしようというのが、T-Timeだった。
エキスパンドブックが「紙の本にいかに電子的に再現するか」ということを意識していたのに対し、T-Timeでは、「オンスクリーンというデジタル時代の紙は伸縮自在なんだということで、その紙という枠をはずしてしまった」。したがって、ある読者が読んでいる本と別の読者が読んでいる本は、内容は同じでも、ページ数はまったく違うということもあり得る。このように、読者自身がいちばんいいような読み方で読めるという「紙の編集者にとってははなはだ冒涜」とも言える側面が、逆に電子書籍ではメリットにつながるとしている。
●「ドットブック」で出版ビジネスを視野に紙の本にはないメリットを提供できる電子書籍だったが、一つだけ大きな欠点があった。それは、出版社などには、このシステムを利用する「客がいない」こと。「現実として、特に日本の紙の出版社はけんもほろろで、電子出版に見向きもしなかった」という。
しかしまったくいなかったわけではなく、アマチュア作家など「紙の出版ができない人」などには広く受け入れられた。「人に何かを伝えたいという気持ちは誰でも持っているもの」であり、「電子出版は将来的にきっと潜在性を持つに違いない」と確信したという。「紙の出版とは無縁な人を対象に、彼らがものを発表するツールを作るというのがボイジャーの仕事だった」としている。
一方、紙の出版に受け入れられないという現象は、紙の出版界自身の内部でも起こった。「専門書や学術書などの売れない本が全部、紙の出版からそっぽを向かれた」ことで、それらが電子書籍化への道をたどった。その結果、「紙の世界の怒涛のような電子化の波と、我々のやってきた波が、この1998~1999年ぐらいからぶつかってきた」。それまで商売や儲けとは無縁だったアマチュア作家をターゲットにしてきたことに加え、出版ビジネスまで視野に入れるときがやってきたわけだ。
この流れを受け、ボイジャーでは2000年に入り、T-Timeを出版ビジネスにも対応できるようにしたシステム「ドットブック/たて書き・立ち読みシステム」を開発した。T-Timeに著作権保護機能や不正コピー防止機能などを追加したほか、電子書店のウェブサイト上で一定時間まで“立ち読み”を許可する仕組みなどが取り入れられている。同システムは、すでに筑摩書房の「Webちくま」や大日本印刷の「銀座の学校」で無料コンテンツ用に採用されているほか、講談社や集英社が電子文庫パブリのメンバーとして9月にも開始するサービスでも導入予定。また、同じく電子文庫パブリにも参加している文藝春秋「文春ウェブ文庫」では、これをベースにした電子書籍リーダーが採用されている。
「僕らは書店でも出版社でもなかったが、マイナーなものからどんどん電子書籍に変わってきて、その動きが非常に大きなものになってくると実感した」という萩野氏だが、電子文庫パブリなどを通じて大手出版社が参入することで、今後は紙の本並みのメジャーコンテンツも電子書籍化されていくことも予想される。電子文庫パブリで扱うのは「とりあえずは、古典や絶版などでしょう」としながらも、必ずしも紙で手に入りにくい本だけが電子書籍の対象ではないという。米国ではスティーブン・キングが新作をネット出版で発表、わずか数日で50万部を販売したが、そういった現象が「日本でもすぐに来る」と見ている。また、逆にネット出版から新しい作家が生まれるなど、従来にはない作家デビューへの「アナザー・パス」を提供する手段でもあるという。
●電子書籍時代の“本”とは
 |
| エキスパンドブックを開発する引き金と なった初代PowerBook。ボイジャーの オフィスに今でも大切に保管されている |
我々が通常、本と読んでいるのはページを綴じた“冊子本”だが、これが登場する前は巻物形式のものが本だった。冊子本の持つページという構造により、読者は目的の部分に容易にアクセスできるようになった。このような大きな変化が、電子書籍にもある。例えば、目次よりもさらに細かく調べられるテキスト検索、文字と静止画だけでなく音や映像まで収録できるというマルチメディア性などである。
そして、ハイパーリンクという機能がある。その本の中の関連部分を簡単に参照できるのはもちろん、リンクを辿りながら読み進むことも可能になる。これにより、もしかしたら、冒頭から順に読み進んでいくという本のリニア性さえ、あたりまえのことではなくなるかもしれない。さらには、インターネットを通じてその本の外にある資料にまでリンクを張ることも可能だ。こうなってくると、本とはいったい何を指すことになるのか? エキスパンドブックを発表した当時、「本とは形なのか、冊子型で束ねられた状態のものを本というのか、あるいは中に書かれていることを本というのか、本とは何ぞやということをまじめに考えていた」という萩野氏に、電子書籍時代の“本”の定義について最後にうかがった。
萩野氏は、紙の本がまったくなくなることはないとしながらも、コンピュータのディスプレイの「習慣性」を指摘する。「本を読んでいるという意識はないが、文字を読んでいるということなら、僕らにとっては電子的な機器を通して読むことが習慣となってきている」ため、紙の本のかたちというのは「いずれにせよ確実に流れ出してくる」という。現在の生活環境を見ると、会社に行けばデスクトップのコンピュータが必ずある。家に帰ればノートブックのコンピュータがある。外出するときは携帯電話やPDAを持っている。「そうすると、会社のデスクトップで買った“本”を家ではノートブックで見る、電車に乗ったときはPDAで見るということはあり得るわけです。そういうふうにして、内容を共有して適当な表示装置で見ていくということはどんどん発達するんじゃないでしょうか。それを総称して“本”ということになる」。ただし、電子化された“本”がディスプレイでしか見られないというのでは不十分で、「(オンデマンド出版により)紙の本で見たい、携帯端末で見たい、ノートブックに落として見たい、自分でプリントアウトして見たい」といったユーザーの「好き勝手に見る」というニーズが保証されるのが、電子書籍の一つの形ではないかとしている。
(2000/8/21)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp / Watchers]