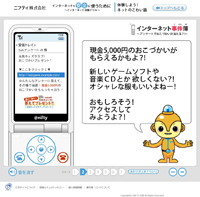|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/05/19 】 |
||
| ||
【 2009/03/19 】 |
||
| ||
【 2009/03/05 】 |
||
| ||
【 2009/02/06 】 |
||
| ||
【 2009/02/05 】 |
||
| ||
【 2009/01/22 】 |
||
| ||
【 2008/12/26 】 |
||
| ||
【 2008/12/25 】 |
||
| ||
【 2008/12/11 】 |
||
| ||
【 2008/10/30 】 |
||
| ||
【 2008/10/24 】 |
||
| ||
【 2008/10/23 】 |
||
|
|
|
||||||||||||||||||
| 10代のネット利用を追う | ||||||||||||||||||
|
“ネットの未来を守るために”ニフティが考えること |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
前回は、東京都品川区立の小学校で導入された、ニフティによる「情報モラル教育」の授業の様子をレポートした。なぜ、ニフティはこのような活動を始めたのか。そして、受け入れた側である教育現場の問題意識はどうなのか。 ● 外部からの協力も積極的に活用する「市民科」の授業
「内容が多岐にわたるため、授業には専門的な知識や情報が必要になります。教師だけで実現するのはなかなか難しいため、外部から力を借りて実現するのは有意義なこと」と、品川区教育委員会指導主事の滝渕正史氏は語る。 今回の授業は、ニフティ側から話を持ちかけられ、教育委員会が導入を決めた。同様に品川区ではこれまでに、外部からの協力を得て、フジテレビのアナウンサーによる話し方教室、日本サッカー協会の協力でJリーグ選手による夢の授業などが実施されている。さらに裏千家によるお茶の授業をはじめ、経済教育団体ジュニアアチーブメントと共済により企業の協力を得て、空き教室に架空の街を作り、仕事の体験学習ができる授業なども行われている。 例えば夢の授業では、Jリーグの選手が挫折をどう乗り越えたか、どのようにして夢を実現したかを語った。「子どもの目の輝きが違いました。一芸に秀でている人の影響力はすごい」。 一方、市民科には当たり前のことを当たり前にできるようにするというしつけ的な面もある。「今までは気が付いたときに叱っているだけでしたが、カリキュラム化してきちんと教えていこうという考えです。傘のたたみ方や礼儀作法などは家庭でやるべきという思いはありますが、学校でやらざるを得ない状況になっているのです」。このような教育活動は、東京以外でも実施しているところはあるものの、品川区は教科書まで作り、全校で同じカリキュラムで実施しているところが一歩進んでいる。教科書は、教員がどうやって教えるか考える手引きになっているそうだ。 ● 携帯電話所持率が高い一方で、保護者の危機意識はまだまだ低い
滝渕氏によると、利用時のトラブルとしてはチェーンメールが一番多く、出会い系サイトやコミュニティサイトによるトラブルもある。掲示板などで誹謗中傷を書かれるトラブルも多い。 「保護者は料金についてはうるさく言うものの、最近はパケット通信料定額制になったため、ルールは何も決まっていないし、子どもは注意もされない状態です。しかし実態は、小学生でも自分の部屋で夜の11時、12時までメールを打っています。問題として表に出ていないだけで、いつ表に出てきてもおかしくない土壌はあるのです」。 ● 今後、学校でも携帯電話などリテラシー教育が必要に 「まずは、子どもにネットをどんな目的でどう使わせるかということを、保護者に認識していただくことが必要だと考えています。携帯電話の使い方は、今後カリキュラム化していきたいですね。ニフティさんに実施していただいたような授業が必要となるでしょう。すぐにメールの返事をしなかっただけで人間関係が崩れるとか、返信をしないと寝られないなどの問題は、実際に起きてきています。携帯メールの使い方や情報リテラシーは、今後取り上げていく必要があるでしょう」。ちなみに、これらの教育を学校の中で扱わねばならないと考える理由は、学校での人間関係に影響を与えるからだそうだ。「今回の授業のように、ネット企業の人がネットの危険性や正しい使い方を教えてくれるのは素晴らしいことです。今日の授業だけで全部理解できたかどうかはわかりませんが、今回の授業を受けたことは次の授業の深まりにつながるのは確かでしょう」。 ● 子供たちが無防備にネットを利用しないよう、、情報モラルの授業を開始
大空氏が所属する社会貢献チームが発足したのは、2007年10月のことだ。「私には小学校6年生の子どもがいるのですが、ネットを使っている時にいろいろと質問をしてきます。そこで、うちで起きることは他の家庭でも起きているのではないかと考えたのです。ネットの会社にいる私なら、子どもに聞かれても教えられます。けれど、親にも子にも知識がなければ、危険なサイトにアクセスしてしまいかねません。ネットは便利な楽しい情報ツールなのに、間違った使い方をしたせいでネットは怖いと思われると悲しい。ちゃんとした使い方を教えたいと思って提案したのです」。 その提案が通り、会社として取り組むこととなった。2008年4月には社会活動推進室もできた。ちなみに品川区で実施しているのは、まずはニフティがある地元で地域貢献をしたいと考えたためだ。このような取り組みは同社初のこととなる。ネットが広まるにつれて闇の部分が顕著になってきており、ネットビジネスを展開する立場として、ネットの被害に遭う子どもを1人でも多く救う責任があると考えての判断だ。 他の地域からも要望があれば、いずれは品川区だけでなく全国的に展開する可能性も視野に入れているが、まずは自分たちができるところから始めていくという。 ● 情報モラルには心と知識の2つの分野、授業ではまず知識を
ちなみに、今回の授業の内容は、ニフティが学校や教育委員会にも見てもらいながら作り上げた。また、子どもたちに危険回避の知識を確実に身に付けさせるためには、違法・有害サイトを擬似的に体験できる「インターネット体験ドリル」をニフティのサイト上で9月から提供し、出前授業の次の単元で復習のために利用できるようにした。なお、このサイトは、品川区の小学校だけでなく、広く誰でもアクセスして学ぶことができる。 「トラブルの原因は、親子のコミュニケーション不足など、家庭での問題が大きく影響していると思います。けれど家庭の中には踏み込めないので、せめて子どもたちを通じて手紙などで保護者の方の意識を高めて、子どもたちの周りで起こっているいろいろな問題に気付いてもらいたいと考えています」。今回も、フィルタリングのかけ方などを保護者あてのプリントにして配布した。さらに、品川区立の小中学校の保護者向けの「情報モラル講座」もあわせて展開をはじめている。講座では、新聞の記事などから実際に起こった事件の事例などを抜粋して、具体例を交えながら危険性をアピールして啓発活動を行っている。 ● 危険を知らない子どもたち、「ネットは便利」の前に教えるべきこと 授業を実施してみての子どもたちの反応や感想についても、大空氏に聞いた。「授業の後、子どもたちに感想を書いてもらっていますが、ネットは怖いと認識を新たにした子もいるし、フィルターをかけたいという感想もあります。危険を正しく認識させるのはいいことだと思いました。子どもたちは意外と、ネットを何も考えないで使っている印象を受けました。ネットには危険な情報や嘘もあるとは知らなかったようです。その意味でも小学校から始めるのが大事だと思います」。ネット企業がネットの魅力を抜きに、怖さや危険だけを教えるというのはもったいない話のように思える。それについては、「正直、ネットの便利な部分も教えてあげたいですが、今はまず正しい知識を教える段階だろうと思っています。“便利さ”は、ネットとは何で、どんなことが起こるかを把握した上でもわかってくるものだと思うので。ネットはインフラ的に必要不可欠になってきているので、いずれ使うようになるでしょう」。 今後、企業もできるところからネットの正しい使い方の啓発活動に励む必要があるだろう。結局はそうすることが、ネットの未来を守ることにつながっていくのだ。 関連情報 ■URL 品川区教育委員会 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/ 新しい学習「市民科」 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/sidouka/plan21/12p21_shiminka.html ニフティ http://www.nifty.co.jp/ インターネット体験ドリル http://www.nifty.co.jp/csr/edu/school/ ■関連記事 ・ “ネットのこわい話”を疑似体験、ニフティが子供向け教育サイト(2008/09/04) 2008/09/05 11:05
- ページの先頭へ-
|