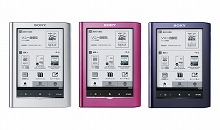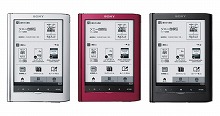電子書籍は現在、コンテンツやデバイス、流通、規格、ビジネスモデル、文化など、さまざまな要素がからみあい、いろいろなアプローチが登場している。このシリーズインタビューでは、それぞれ異なる方向から新しい市場に取り組むキープレイヤーに話を聞く。
出版社やメーカーとは違う方向からのアプローチとして、paperboy&co.では一般の人がブログ感覚で電子書籍を作り、販売できる、「ブクログのパブー」を提供している。シリーズインタビュー第6回は、paperboy&co.取締役副社長 経営企画室長の吉田健吾氏に、「ブクログのパブー」とその母体となったオンライン蔵書管理サービス「ブクログ」について話を聞いた。
● ウェブで作れる個人出版サービス
 |
| paperboy&co.取締役副社長 経営企画室長の吉田健吾氏 |
―― ブクログとパブーを始めた経緯を教えてください。
吉田:「ブクログ」はもともと前社長の家入(一真氏)が2004年ごろに個人の趣味で始めた、インターネット上に自分の「本棚」を作成できるサービスです。ユーザーも20万人ぐらいまで増えたものの、家入が多忙になってあまり対応ができなくなり、ユーザーの要望にも応えられていませんでした。これはもったいないということで、事業を会社に譲渡してもらいました。
ブクログを事業化する際に気付いたことなのですが、インターネット上には書籍をプロモーションする場所が少ないんですよね。自分が本を買う場合で考えても、有名なブログで紹介されていたり、Twitterでフォローしている人が面白かったと書いていた本を買うぐらいです。そこで、インターネット上で本を見つけられる「人と本が出会う場所」というコンセプトを決めて、ブクログをリニューアルしました。
ブクログの事業を始めて、出版社の人と話すようになった中で、電子書籍の波が来ているということを知りました。特に米国でKindle DTP(現在はKindle Direct Publishing)のサービスが登場して、個人でも電子書籍を出せるという話に興味を惹かれました。マンガ家のうめさんが、自分で「青空ファインダーロック」という本を公開したという話も大きかったですね。
一方で、パブーにつながる伏線としては、社内のプレゼン大会で「ウェブ上でマンガを公開して共有する」という企画が上がっていたんです。その関係で、個人出版についてもリサーチを続けていました。また、ブログサービスの「JUGEM」を運営していく中では、ただの日記にとどまらないコンテンツを書かれる方もたくさんいて、そうしたコンテンツが書籍化されるという経験も多くありました。それらが揃って、2010年の年始ごろに、電子書籍のサービスを作ろうと決めました。ブクログとなるべく連携させたかったので、「ブクログのパブー」という名前で、IDも共通でスタートしました。
―― パブーはブログのようなインターフェイスで電子書籍が作れるので、ブログから発想したサービスかと思っていたのですが、ほかの流れもあるのですね。
吉田:そういう意味では、先にブクログのサービスがあったことが大きいですね。そして、Kindle DTPを見たときに、一般の方も電子書籍というフォーマットで発表できるようになる世界になるだろうと確信したこともあって、ブクログでコンテンツの売買もできるようにしたいと考えて、サービスを作りました。
海外では、Kindle DTPやSmashwordsといった個人出版のサービスがいくつかありましたが、原稿をWordなどのファイルでアップロードする形式のものが多く、ブログのようにウェブ上のエディターで書けるものは見当りませんでした。ブラウザーで書けるほうが、さらに敷居が下がるだろうと思って作ったのがパブーです。我々は元々ブログサービスをやっていて、そのあたりは得意でしたので。
電子書籍の形式にEPUBを採用しているのも、EPUBの中身はHTMLなので、ウェブの会社である我々として扱いやすいという利点がありました。
―― 個人でも電子書籍を出す人が増えると確信したのはなぜでしょうか。
吉田:いちばん大きいのは、ブログのサービスをやってきた中で、表現したい人がたくさんいると皮膚感覚で感じたことです。また、電子書籍の特性として、少部数でもページ数が少なくても作れるということがあります。マンガ家さんからも、雑誌に描いた読み切りは、短編集を出すことなどがなければ出す機会がなく、そうした埋もれている原稿がけっこうあるといった話を伺いました。
小さなコミュニティの中で必要とされている情報もけっこうあります。たとえば、特定の疾患を持った方に役に立つ情報といったコンテンツは、母数が少ないので紙の書籍ではなかなか出せない。ブログでもいいんですが、それでは対価が発生しない。まとまった小さめのコンテンツが流通して、ちゃんとお金が動く形を作れば、役に立つんじゃないかなと思いました。
● 日本語のEPUB書籍を一番多く作っているのはパブーかもしれない
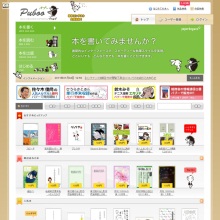 |
| ブクログのパブー |
―― 現在、パブーにはどのくらいの電子書籍が登録されているのでしょうか。
吉田:現時点で8218冊で、日々増えています。ダウンロード用のフォーマットはEPUBとPDFを用意していますが、たとえばスマートフォンで見る場合だと、マンガはPDFの方が見やすいとか、文字中心のものはEPUBの方がいいといったこともあって、両方用意しておきたいと思っています。また、ブラウザーで読むためのウェブ版もあって、ウェブ版を置いておくことで検索エンジンからの導線も作れます。
どのコンテンツにも、EPUB、PDF、ウェブ版の3つのフォーマットが用意されています。もしかすると、iPadで読める日本語のEPUB書籍を一番多く作っているのはパブーかもしれません。
―― 現在のユーザー数はどのくらいでしょうか。
吉田:読者さんと著者さんを合わせたユーザー全体で2万人を超えています。そのうち、作品を公開している著者さんは、正確な数字ではありませんが、3000人ぐらいです。
ユーザー層としては、元々はJUGEMのユーザー層を想定していました。JUGEMは20代の女性が中心のブログサービスなので、女性が6~7割という感じです。パブーのユーザー層は、それよりもう少し上の方が目立つように感じています。また、割合として多いというほどではないのですが、60~70代の方が、詩集や写真集などを公開されているケースもよく見受けられます。これまでは、紙の自費出版を利用されていたような層なのかなと感じています。
―― 実際に売れている例などがあれば教えてください。
吉田:トータルで一番売れているのは、うめさんや佐々木俊尚さんのようなプロの方の本ですね。プロの方々にとっては、まだこれだけで商売になるというほどではありませんが、今後を見据えて試していただいているところだと思います。
サービスのターゲットとして考えていたのは、インディーズというかセミプロというか、専業ではない方にとっての収入源となるものです。そのためには、読者数をもっと増やさないといけないと思っています。
 |
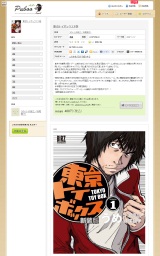 |
| 佐々木俊尚氏の「本当に使えるウェブサイトのすごい仕組み」 | うめ氏の「東京トイボックス」 |
―― 手数料はどのぐらいでしょうか。
吉田:売上の30%をいただいていますが、無料で公開されている場合や、売上が発生していない場合などには手数料はかかりません。
―― ブログの記事を書くようなインターフェイスで簡単に電子書籍が作れるのは便利なのですが、一方でプロの人などにとっては、より細かいレイアウトなどを指定したいという要望もあるのではないでしょうか。
吉田:その要望については、完成したPDFファイルをアップロードしてもらい、EPUBとウェブ版に展開して公開する方法を検討しています。ウェブのエディターで複雑なことをできるようにしても、EPUBとPDFの違いなどもあって、コントロールできる範囲が限られてしまいます。ウェブのエディターはいまぐらいのシンプルなものにとどめておいて、より複雑な組版やレイアウトをしたい場合はデータをアップロードしてもらう形がよいかと思っています。
ただ、PDFをアップロードできる形にすると、スキャンした本を無断で登録してしまう海賊版のような問題もありますので、有料版のサービスとして提供する形になると思います。
● 同じ本を無料版と有料版で提供、想定していなかった使われ方も
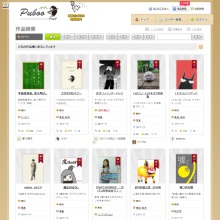 |
| パブーの総合ランキング |
―― 個人制作の本というと、コミケのようにマンガが中心になるのかと思っていましたが、パブーに並んでいる本を見るとそうでもありませんね。
吉田:総数でいうと小説がいちばん多いですね。パブーは二次創作はNGという利用規約になっていることも影響があるかもしれません。小説の中でも、ファンタジーもあれば、純文学もSFも、ライトノベルもありますし、ジャンルはけっこう散らばっています。
あと、ビジネス書のようなものを書いていらっしゃる方もいます。株の投資の方法を書いている方や、マーケティングや企画のバックグラウンドを持つ方が自分の経験にもとに本を出していたりもします。
―― 当初想定していなかった、パブーの面白い使い方をされている例がありましたら教えてください。
吉田:街中にバリカンを持って出掛けて、女の子に声をかけて、自分の頭を一刈りずつ刈ってもらい、最後に丸坊主になるまでを写真集のような感じでまとめた「美人バリカン」という本を出した方がいらっしゃいました。基本は無料で公開されているんですけど、全く同じ内容の本を200円版と500円版の有料版としても出していて、面白いと思ったら買ってくださいという、投げ銭のようなことを試していました。
また、ゲームクリエイターの方で、「ドリトル先生物語」を自分で飜訳して、同じ内容を別々の人にさし絵を描いてもらって別バージョンの本として出している方もいらっしゃいます。
パブーでは、有料の本でも立ち読みできる範囲を著者が設定できるようになっています。この機能を使って、全部のページを立ち読み可能にした上で、値段を付けている例もあります。ウェブで全ページが読めますが、ダウンロードは有料になりますので、これも面白かったら買ってくださいという使い方ですね。
● フォーマットは、一般の個人が作って読めるものを採用
―― 今後、EPUBやPDF以外にフォーマットを増やす予定はありますか。
吉田:我々としては、いろいろな形式で公開して、いろいろなデバイスで読める方がいいと思っています。
EPUBとPDFを採用しているのは、比較的オープンな規格で扱いやかったためです。あまりコストをかけられないこともあって、ライセンス料が発生するフォーマットではなくEPUBとPDFを採用していますが、種類を増やしたくないということはありません。
PDFならサードパーティでもリーダーを作れますし、EPUBにしても中身はHTMLなのでブラウザーでも見られます。ユーザーとしては、自分が持っているコンテンツが開けなくなってしまうことは避けたいですし、著者の方に負担もかけたくない。そういう意味では、オープンなフォーマットでやっているという点を、安心感として受け取ってもらえればと思います。
―― その話とは逆の流れになるとは思いますが、DRMに対応する予定はありますか。
吉田:たぶん、ほかの電子書籍サービスとパブーが一番違うのは、DRM無しの方針でやっていることではないかと思います。一般の個人の方に、なるべく広くたくさん読んでいただきたいという方針のサービスなので、DRMはかけないほうがいいだろうなという判断です。
ただ、メールアドレスを埋め込むような「精神的DRM」のようなレベルであれば良いかなとは思っていて、ちょっと考えています。「電書フリマ」をやっている電書部さんなどが採用している方法ですね。
―― 現在の利用者は、主にどのようなデバイスで読んでいるのでしょうか。
吉田:ダウンロードされるファイルでいうと、EPUBが多いコンテンツと、PDFが多いコンテンツの両方があります。我々も調べているのですが、たとえばマンガや小説といったジャンルでは傾向の違いがはっきりとは出ないので、まだよくわかっていません。PDFはPCでも読めますが、EPUBはスマートフォンやiPadのユーザーが多いだろうと推測するぐらいですね。あと、ウェブ版だけで見ている方も多いですね。
● 複数人が共同で本を作るための機能なども提供していきたい
 |
―― 読者をもっと増やしたいという話がありましたが、そのための今後の課題は?
吉田:サービスとしては、100円程度の少額決済ができるようにする必要があったので、我々の「おさいぽ!」という決済システムを利用していました。
ただ、やはりIDを登録しなくてはならないのがハードルになっていた部分もあったので、ID無しでもカード決済できるように変更しました。これで少しハードルが下がって、これまで購入していただけなかった方にも買っていただければと思っています。
―― 今後、増やしたい電子書籍のジャンルはありますか。
吉田:個人的には、ビジネス書や新書、実用書のようなものは、電子書籍に向いていると思っています。特に時事性の高い内容の書籍は、比較的短いスパンですぐに発売して、後から内容のアップデートもできるという電子書籍の特性に合っているのではないかと思うのですが、まだそれほど多くないんですよね。
―― パブーで絵本のコンテストもやっていましたね。
吉田:はい。もともと絵本は、開始直後からコンスタントに公開されていました。バブーのサービスを開始するときに、こんな雰囲気というサンプルとして絵本を出したんですね。そのときの印象や、サイトのイメージ、ユーザー層などから、絵本も多くなっていると思います。
そうした中で、コンテストの第一弾としては絵本がいいんじゃないかということになりました。我々は本については素人なので、小説だと審査も大変だなということもありまして。コンテストは今後も継続的にやっていきたいと思います。
―― パブーで今後提供したい機能はありますか。
吉田:複数人で1つの本を作っていく機能は入れたいと思っていて、提供予告もしています。絵を描く人、文章を書く人、企画を立てる人とか、何人かで1つのコンテンツを作るための機能です。インターネットのよいところは、遠隔地の人とでも、もともと友達どうしでない人ともコミュニケーションできるというのがありますので。現状でも、いっしょに本を書く人をTwitterで探しているというケースを見かけるようになりましたので、サービスとしてサポートできるようになるといいなと思います。
―― 吉田さん自身はパブーの本を読んだり書いたりは?
吉田:けっこうマンガは読んでいますね。あと、子供にiPadで絵本を見せると機嫌がいいので、いろいろダウンロードしています。
自分で書いてはいませんが、うちのスタッフが先日「パブー合宿」というのをやりまして、各人が好きなものを作っていました。マンガを描く人もいれば、書きかけの小説を完成させるとか、会計について書くとか、いろんな人がいましたね。
―― 最後に、パブーで本を書いている方や読んでいる方にメッセージを。
吉田:書いていただいている方には、複数人で本を作るための機能や、自分たちの本がどのように読まれているのかがわかるアクセス解析のような機能などを、もっと強化していきたいと思っています。
あと、著者と読者のコミュニケーションを取れる仕組みとして、読んでもらっている手応えがわかるものをなにか作りたいですね。たとえば、「いいね!」ボタンのようなもので、読んでいる途中にここが面白いというのを著者さんに伝えられると、励みになるかなと考えています。
読んでいただいている方に対しては、まだ街の本屋さんに比べると冊数が少なく、その分面白いと思える本に出会える確率も低くなるので、もっとコンテンツを増やしていかないといけないと思っています。
ただ、マンガや絵本は、今でも読んでいただければ、たぶん好きなものが見つかるんじゃないかと思います。小説ですと、好みのジャンルも分かれていたり、読んでみないと面白いかどうかわからないという部分もありますが。そういう意味で、我々としても面白いものをお伝えできるような仕組みも作っていきたいと思っています。