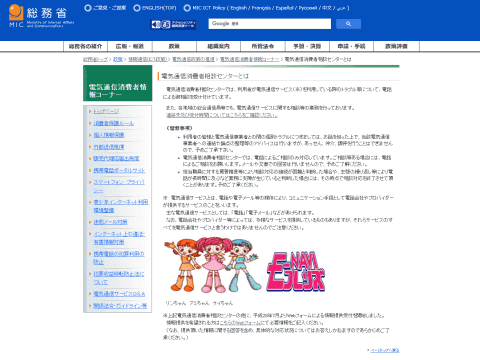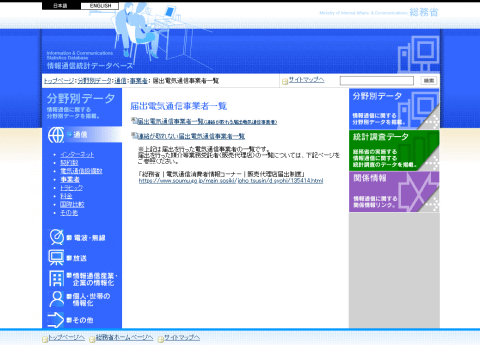特集
レンタルサーバー事業者がある日突然サービス停止!? そんな事態に利用者はどう備えるべきか?
2025年11月26日 06:00
もしも、利用しているレンタルサーバーなどのサービスが何の告知もなく突然サービスを停止し、連絡も一切取れない状態になってしまったら、データの回収も難しく、大変な損害につながってしまうおそれがある。
これまで、あまり想定されていなかった問題だが、先日、実際にそのような事例が発生した。どのようなサービスの事業者も、長く運営を続ける中で状況が思わしくなくなり、突然サービス停止に至る、ということは、今後もあるかもしれない。そのような事態に遭遇した利用者ができること、および、そのような事態を避けるために利用者が今やっておくべきことを、総務省および国民生活センターへの取材をもとに解説する。
電気通信事業法が保護する利用者の利益は限定的
今回は、レンタルサーバー事業者を例として解説を進める。
レンタルサーバーのようなサービスを提供する事業者は、電気通信事業法による規制を受ける。同法は、1985年のNTT民営化、電気通信事業の自由化にあたって施行された法律だ。
同法では、「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること」を電気通信役務と定義し、それを事業として営む事業者は、総務省に届出を行う必要がある。そして、届出を行った電気通信事業者を「届出電気通信事業者」と呼ぶ。つまり、レンタルサーバーをはじめ、インターネットのサービスを提供する事業者のほとんどは届出電気通信事業者である(ほかに、NTT東西などの「登録電気通信事業者」も存在する)。
電気通信事業法では電気通信事業者に対してさまざまな義務を課し、利用者の利益を守っているが、多くは携帯電話事業者や回線事業者(ISPなど)を想定した内容であり、レンタルサーバー事業者に該当する内容は、それほど多くない。主要な義務には、事業を休廃止する際に周知する義務(第26条の4)、事故などで業務が停止したときに報告する義務(第28条)があるが、提供条件の説明義務(第26条)、書面の交付義務(第26条の2)などは、レンタルサーバー事業者には当てはまらない。
行政の相談窓口は総務省と消費者庁の2つがある
利用しているサービスにおいてトラブルが発生し、事業者と連絡が取れない、または事業者に問い合わせても誠意ある対応をしてもらえないというとき、相談できる公的な窓口は2つある。
1つは、総務省の「電気通信消費者相談センター」で、電話またはウェブ上のフォームから相談が可能だ。ただし、総務省の窓口はトラブル情報の収集窓口の性格が強く、寄せられた情報を収集して今後のルール作りに役立てられるが、困っている利用者を助けるために事業者に働きかける権限はない。
もう1つは、消費者庁が管轄している窓口で、188(いやや)番の消費者ホットラインが分かりやすい。消費者庁が管轄する国民生活センターでは、解決に向けた「裁判外紛争解決手続」(ADR)や「消費者団体訴訟」という制度も持っており、アドバイスだけでなく、事業者に対する介入や仲介・仲裁もしてくれる。すべての相談・申請に対してこれらの制度が適用されるわけではないが、被害の回復や契約における問題の解消を目的とする場合は、こちらの方が適当だ。
まずは消費者ホットラインに相談すれば、相談員から適切な制度の利用に関して助言や説明を得られるという。また、一般的に、相談の件数が少ないよりは多い方が、介入等が行われる可能性が高まる。
▼各相談窓口のリンク
電気通信消費者相談センターとは(総務省)
申出・問合せ窓口(消費者庁)
規約の確認やバックアップで自衛し、事業者が信頼できるかチェックを
こうしたトラブルに遭遇しないようにするために、有効な方法は? と総務省の担当者に伺ったところ、一般論にはなるが、契約時に利用規約やサービス内容の説明をよく確認し、自衛することが大切、とのことだった。
特に、サポート体制や、トラブルによるサービス長期停止時の補償、トラブルに備えたデータバックアップの方法といった、いざという場面の対策について確認しておくべきだろう。
また、レンタルサーバーのような、事業者のサーバーにデータを預けるサービスの場合、急にサービスが停止して事業者と連絡が取れなくなってしまうと、データを失うことになってしまうことが大きな痛手になり得る。定期的に手元へデータをバックアップすることや、事業者のデータ保護体制について確認しておくことも、重要となる。
総務省のウェブサイトでは届出電気通信事業者の一覧を公開しており、同じページで、「連絡が取れない届出電気通信事業者一覧」も公開している。
これは、総務省が届出電気通信事業者に対して連絡が取れるか確認を行った際に、返信がなく連絡が取れなかった事業者を一覧にしているもので、「連絡が取れない理由はさまざまで、この一覧に載っていることがただちに問題があることを示すわけではないが、参考までに」公開しているものだという。
▼届出電気通信事業者の情報
届出電気通信事業者一覧(総務省)
事業者は利用者の信頼を得る努力を
総務省の担当者に、サービスを提供する事業者に対して伝えるべきことがあるかと伺うと、「利用者に対して真摯かつ丁寧にサービス内容を説明し、理解を得ることに努めてほしい」とのことだった。
多くの事業者にとっては言われるまでもないことだろうが、利用者を心配させるような事業者は、支持を得るのは難しいだろう。
事業者が突然サービスを停止した事例
冒頭で述べたように、実際にこのような事例があった。2025年10月、レンタルサーバーやドメイン取得代行などのサービスを提供する事業者が突然サービスを停止したと、複数の連絡や情報提供を編集部にいただいた。
同事例では、同事業者や同社が提供するサービスのウェブサイトが1週間以上何も表示されない状態になっていたが、その後、サービス運用のためのデータセンターの料金が未払いになり、停止したとの事情説明をウェブサイトに一時掲載した。その後、順次サービスを回復させているようだ(事情説明は現在非公開になっている)。
同事業者のサービスを利用していた方に伺ったところ、本件について同事業者からメールなどによる説明や謝罪は一切なく、ウェブサイトに一時掲載していた説明が、得られた情報のすべてだとのことだった。また、編集部では同事業者のウェブサイトに掲載しているアドレスに質問のメールを送ったが、2週間以上経った現在でも返信はない。なお、同事業者は2025年11月現在の「連絡が取れない届出電気通信事業者一覧」に載っている。
この件は、事業者の説明によればデータセンターの料金未払いが原因ということで、業務が停止したときの報告義務に該当するのか、判断が難しいようだ。また、事業を再開しているならば、休廃止する際の周知義務が該当するかも判断が難しいという。取材時に総務省の担当者が「法律も想定していなかったケース」と話していたのが印象的だった。
インターネットのサービスの多くは、日々問題なく利用できていれば、事業者のウェブサイトなどをチェックする機会はあまりないだろう。10年前、20年前に契約したサービスを、ずっと使い続ける人も少なくないと思われる。
長く利用しているサービスの事業者には何となく信頼感が生まれるし、乗り換えなども面倒に感じられてしまう。しかし、そのような「ほったらかし」状態はリスクであると認識して、定期的に事業者の状況を確認し、利用規約の変更状況なども確認し、また、バックアップを取って、万が一に備えておくべきだろう。