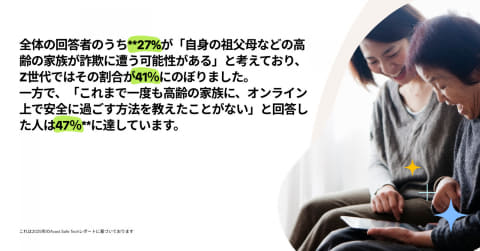ニュース
Avast、日本の高齢者を狙うサイバーリスクを警告し、家族で話し会う時間を持つことを推奨
2025年7月23日 06:30
Genは7月22日、同社のコンシューマー向けセキュリティブランド「Avast」が実施した調査のレポート「Avast Safe Tech Report」を発表した。そして、日本の高齢者がさらされているセキュリティリスクに対し、子ども世代が十分な話し合いなどをしていないことを指摘し、「ネット詐欺やサイバーリスクについて話し合う時間(Safe Tech Talk)」を持つことを呼び掛けた。
Avast Safe Tech Reportは、日本のほか11カ国で実施。日本では2025年4月30日~5月9日に、18歳以上の消費者1000人を対象に、オンラインで実施された。結果は年齢・性別・地域で必要に応じてウェイトをかけ、全国の代表値としている。
高齢家族を持つ27%が被害を経験も、47%は「教えたことがない」
回答者の27%が、高齢の家族がオンライン上で何らかの被害を受けた経験があると回答していることがわかった。主なオンライン上での詐欺の手口としては「メール」と「電話」が共に47%を占めている。また、Z世代の41%が、高齢の家族の詐欺被害を懸念している一方で、47%は高齢の家族に安全なインターネットの使い方を教えたことがないと回答している。
回答者の62%が高齢の家族に対してリスクのあるオンライン行動や詐欺について警告しようとした経験があるが、警告を受けて実際に行動を変えた人は50%にとどまっていることがわかった。その他の人たちは無視したり、「自分は大丈夫だ」と言っているとの回答があったという。
ネット詐欺やサイバーリスクについて話し合う時間(Safe Tech Talk)
同社は、家族や大切な人と「ネット詐欺やサイバーリスクについて話し合う時間」(Safe Tech Talk)を持つことを推奨している。高齢の家族に限らず、話し合い、共有するべきことの例として、「不審なメッセージや電話を受け取った際、会話のきっかけとして家族と共有する」「個人情報やデバイスの管理方法についての話し合い」「インターネットの安全対策を共有する」といったことを挙げている。
そのほか、以下の対策も実施することで、より安全に高齢者が利用できるとしている。
強固なパスワードを使用する
それぞれのアカウントでパスワードを使い回さず、小文字・大文字・数字・記号を組み合わせた長いパスワードを使用する。また、誕生日や名前などの個人情報を使用することを避け、必要に応じてパスワード管理ツールの活用も検討する。
怪しいメッセージを見抜く
銀行、医療機関、テクニカルサポートなどを装ったメール・SMS・電話には注意する。詐欺の場合は緊急性をあおり、すぐに行動させようとする傾向があるという。
高齢者を狙う詐欺の手口を知る
フィッシング、テクニカルサポート詐欺、ロマンス詐欺、偽請求書、偽ソフトウェア更新などが挙げられる。
デバイスのセキュリティに注意する
デバイスやアプリを常に最新の状態にし、セキュリティ対策ソフトなどでデバイスを保護する。