
2002年・激動のオークションシーン~主要プレイヤー各社に聞く
Yahoo!オークションの手数料課金導入、BIDDERSが打ち出したYahoo!への対抗姿勢、またeBay Japanの終了など、2002年のインターネットオークション業界の動きは激しかった。この荒波を乗り越え、それぞれのポリシーで展開してきた各サイトの次の一手とは? 2002年も終わりに近づいている今回の特集では、オークションの主要プレイヤー各社から、2002年を総括と今後の展望を伺った。さらにオークションを知るには欠かせないサイトの裏側も訪ねてみた。
・トップランナーの余裕とこれから~「Yahoo!オークション」
・目標には達しなかったが、得たものは大きい~「BIDDERS」
・オークションは取引方法のひとつ~「楽天フリマ」
・のどかな趣味の場から荒海へ~「WANTEDオークション」
・オークションデータの宝庫の裏側~「オークション統計ページ(仮)」
http://auctions.yahoo.co.jp/
 課金導入前の“駆け込み出品”で最高時420万点の出品数を記録し、課金導入後は一時200万点を切るまで下落した「Yahoo!オークション」。その後は再び増加し、今は1年前と同程度の310~320万点が出品中だ。「半分くらいまで下がることは予想していました」と、ヤフー株式会社オークション事業部長の事業部長・殿村英嗣氏は言う。
課金導入前の“駆け込み出品”で最高時420万点の出品数を記録し、課金導入後は一時200万点を切るまで下落した「Yahoo!オークション」。その後は再び増加し、今は1年前と同程度の310~320万点が出品中だ。「半分くらいまで下がることは予想していました」と、ヤフー株式会社オークション事業部長の事業部長・殿村英嗣氏は言う。
「いいサービスをやっていれば、皆さんまた戻ってくると考えていました。逆に課金を始めてから、落札率が非常に上がった。半分の出品率で倍の落札率になった状態で、これは嬉しい誤算でした。現在の落札率は42~58%前後。曜日や時間でも違いますが、1週間で見ると、週末に落とす方が多いですね。土日に落札してすぐに取引っていう。時間帯は夜のほうが多いです。Yahoo! JAPAN全体だとピークタイムが前倒しになってきて、ゴールデンタイムにかかる20~21時からのアクセスが増えていますが、オークションはまだテレホーダイの時間帯に近いところに集中しています」
システム利用料によって架空の出品や、同一商品の複数カテゴリーへの出品などは大幅に減った。とはいえ、手数料課金を防ぐ目的で“売価は落札価格の100倍”、“1円で即落札、実際の売価は1万円”といった怪しげな条件の出品が目立つ時期もあった。これらは7月に削除対象となることを発表、現在は少なくなっている。
「たとえば10円の落札代金の品物に対して、1万円の送料っていうのはまずありえないですから、そういうのは臨機応変に対処しています。出品をすべて見るのは不可能なので、出品時にキーワードでフィルタリングして、それから必要に応じて人が見て確認する形をとっています。落札者に3%手数料を要求するのも、基本的には良くない。規約でも出品者負担としています。今はケースバイケースでの対応ですが」
トラブルといえば、最近高い評価ランクを得ているユーザーによる詐欺行為が目立つ節がある。こうした状況はどう見ているのだろうか。
「何かしたいのはもちろんですが、どうしたらよいものか…。評価が悪い人はもちろんチェックしていますが、普通明らかに悪いと他の方もやりとりしない。プラスだったのがいきなり悪くなるケースをどうしたものか。システマチックな排除は難しいので、落札後に連絡をとったときにちゃんと返事をくれるとか、かけても通じない電話番号を伝えてくる人は怪しいとか、そのへんのコミュニケーションをしっかりやっていただくか、エスクローを使ってもらうしかない。例えば高価なところで大量に出している場合は、ちょっと気をつけるとか。先日も金券のカテゴリーではエスクローを使ってください、でないと保証の対象になりませんとお知らせしたんですが、現金化しやすいものは特に気をつけてほしいです。こうしたトラブルを防ぐ方法と利用法をまとめたガイドブックも作っています」
課金導入後は、出品時の有料オプションや画像検索サービスなどの機能が新たに加わった。
「利用数で言うと、“背景色”が思ったより使われていますね。あとは“注目のオークション”。マーチャント(Yahoo!と法人契約をしている出品者)はオプション利用料が優遇されるんで、ほとんどの方が使われています。マーチャントでは出品や落札後の手続きを簡素化するツールも提供しているで、大量出品している個人事業者の方に、こちらからマーチャントをお勧めすることもあります。また課金導入後の整備として、サーバーの追加は随時行なっています。新しい、スケーラビリティの高いシステムも現在構築中です。420万点あったときは一時かなり遅かったんですが、今度400万点になったときはそうならないように、今準備しているところです」
課金導入後半年が過ぎ、結果としてYahoo!オークションの王座は揺るぐことがなかった。今後目指す形はどんなものになるのだろうか。
「目指しているのは日本人全員がYahoo!オークションを使うこと(笑)。それは大げさですが、サービスとしては、完成する姿はないと思っています。通信環境も変わるし、その時々のニーズを読みながら機能を増やしていく。ただ、あまり小難しくしちゃうと入るときのハードルが高くなるんで、分かりやすくした上で、オプションとしていろんな機能を備えていきたいです。
Yahoo! JAPANのユニークユーザーは現在約1,000万人ですが、本人確認をしているユーザーは数百万人。今後これをもっと伸ばしていく。またブロードバンドの普及で、いきなりブロードバンドでインターネットを使い出した初心者の方と、3年くらい前からやっている方が同居していると、知識やスケールのギャップをがどうしてもあるんですね。それをどうクリアするかも課題です。
あと、例えば今オークションで出品しようとすると、5個くらいのステップを必要とするわけです。IDを作る、ウォレットを作る、メール認証をする、オークション開始手続きをする、出品する…ってあって、この流れがバラバラになっている。これを1ページで分かりやすく実現できる形を目指しています。セキュリティの問題もあるので、ハードルを下げるんではなく、越えやすい流れを作ってあげるという。
華々しいサービスや機能追加などもやりたいですが、裏の作業がむしろ重要だし、僕たちはプラットフォームを作れればいい。コンテンツを作るのはユーザーさんで、ここまで面白くできてるのはユーザーさんのおかげです。なので、土台作りに徹したほうがいいと思っています」
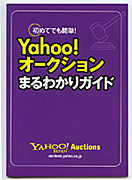 |
 |
| オークションのハウツーをまとめた「Yahoo!オークションまるわかりガイド」 | 現在「クリスマス特集2002」内で、クリスマス向けのお勧めカテゴリーを紹介している |
(2002/12/2)
[Reported by aoki-m@impress.co.jp]