
アラン・ケイ博士の講演などで構成
「コンテンツフロンティアin京都2003」が開催
■URL
http://www.jdaa.gr.jp/info/m0301-29.html
 |
| 講演を行なうアラン・ケイ博士 |
基調講演には、パーソナルコンピュータの父として有名なアラン・ケイ博士が招待された。博士はこの4月より京都で実施される「アラン・ケイプロジェクト」の主要メンバーであり、昨年末にも京都で講演会を行なっている。今回は「子どもたちとパーソナル・コンピューティング」というテーマで、LAで自ら代表を務めるViewpoints Research Institute, Inc.で実施している教育プロジェクトを始め、IT時代の情報リテラシー教育などについて語った。
●コンピュータは楽器のように身近なものになる ~アラン・ケイ博士冒頭でアラン・ケイ博士は、メディア変革の歴史を解説し、印刷革命のように、コンピュータが社会に大きな変革をもたらしたと語った。
「1968年にはコンピュータはより身近な存在になり、シーモア・パパートらとその研究を進めたが、子どもたちのほうがより新しいことを早く学べると感じ、教育に興味を持つようになった。その過程で『squeak』というソフトを開発したが、それはあくまで道具であり、ゴールではない。squeakを使えば、大人の専門家が使うような数式や科学シミュレーションを、おもちゃで遊ぶように疑似体験できる。我々は子供を大人より能力が劣ると思っているが、squeakを使うことに関して言えば、5~6歳の子供でも簡単にプログラミングができ、同時にその意味も理解できている。また子供たちは新しいアイデアをどんどん付け加え、そこからさらに深くて難しいことも学んでいく。そこには数学や科学を学んでいるという意識はほとんどない」
このsqueakを使った学習例として、LAの学校の授業内容を紹介した。例えば“重力の実験”では、子供たちの目の前で重さの異なる球を建物の上から落とし、落ちる速度を計ったりビデオに撮ったりして、後からsqueakを使って分析するというものだ。聞けば難しそうな引力の法則も、視覚化することで理解度が深まるほか、この実験を行なう過程で、子供たちはパソコンを使うだけでなく、実験の様子を紙にメモすることも自然に学んでいた点は注目したいという。
アラン・ケイ博士は、これからの教育に必要なものとして“コラボレーション”をあげ、その新しいツールとして、デヴィッド・スミス氏らの開発したコラボレーションソフト「Croquet」を紹介した。3Dの世界を自由に行き来しながら、その中で書いた魚のイラストを即座に立体化して、泳がせて見るといったことができる興味深いソフトだ。「重要なのはディスカッションすること。世界を結んでコミュニケーションするといった中で、本当にわくわくすることが起きると考えている」という。
講演終了後も会場内から次々に質問が投げかけられ、30分近く質疑応答が行なわれた。そのなかで訊ねられた現在開発中の教育プログラムについて、「現在、スタッフと一緒になって、本当に数学や科学を理解するためのツールの開発を進めている。90%の子供が理解してAをとってくれればいいと思っているが、現段階では70%がAをとれる状態になっている。それ以上理解度を深めることは、教える我々側の問題だろう」と語った。
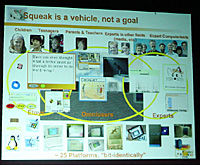 |
 |
| Squeakの概要図 | 身振りを交えながら熱弁 |
 |
 |
| Croquetのデモ。2台のパソコンで共同作業ができる | Croquetの開発者、David A.Smith氏 |
●メディアの進化と技術の進化が京都に新しいものを生み出す
同時開催となった「第4回デジタルフロンティア京都」では、デジタルアーカイブ事業の推進に貢献した団体・個人を表彰する「デジタル・アーカイヴ・アウォード」の表彰式や講演が行なわれた。アウォードでは、電子図書アーカイヴの「青空文庫」や、ミズノによる有名画を水着デザインに再現した「スピード プールサイド・ミュージアム」など5団体の事業が表彰された。また審査員特別賞として、ナック映像センターによる「原爆ドームとその周辺のデジタル復元」など3作品も選出された。
続いて行なわれたデジタルアーカイブやデジタルコンテンツ動向に関するセミナーでは、まずメディアプロデューサーの長屋龍人氏が「メディアの進化と放送文化」をテーマに講演を行なった。同氏は報道番組のプロデューサーやNHK放送文化研究所の研究主幹を務め、30年間テレビ番組を作ってきた経験を活かして「NHKのTV番組50年」という本を上梓したばかりだ。
長屋氏は講演で、メディアがニーズを喚起して、新たなコンテンツが登場することを説明。例として天気予報を挙げ、こうした形になったのは最近であることを指摘した。「テレビが始まって20年間は気象観測衛星がなく、6時間や12時間先の天気しか予報できなかった。気象衛星『ひまわり』が登場した80年代前半に、ようやく今のスタイルに近づいた。今では情報のデジタル化によって地域毎の細かい天気予報ができるようになったが、それはテレビでニーズが喚起されて登場したものだ」という。
またテレビが与える影響について、「人は一日約3時間テレビを見ており、それは人生の約10年間を占めることになる。これが精神的に影響を与えないわけはない」と、明らかな影響があることを認めつつも、具体的にするのは困難だと指摘する。「“一番影響されているものは自覚できない”とマクルーハンが言うように、持続的で有機的で断片的であるがゆえに、放送を語ることは難しい。テレビは場所と時間を開放しているが、今後、サーバー内蔵テレビの登場などで、記憶をも開放するだろう。さらにもっと長い時間が過ぎて、はじめてテレビ文化の影響というものが見えるのではないかと思う」と結んだ。
次いで今イベントの協賛団体の一つである「デジタルコンテンツ協会」(DCAJ)常務理事の工藤浩輔氏から、国内のデジタルコンテンツ事業の流れ、また同協会の取り組みなどが紹介された。
デジタルコンテンツ事業には現在文化(公的)と産業(民間)の2つの流れがあり、それぞれ独立した展開に加え、組み合わせて動くことも多いという。工藤氏は「デジタルコンテンツ事業の第一段階は、素材を探して記録することだったが、今は次の活用の段階に入っている」と説明。その例として、江戸城の中をCGで再現したバーチャルセットの活用を挙げた。また重要文化財の褪色、欠損した素材の再現などをCGで行なう作業も進んでいる。また国の取り組みとしては、文化庁が1,000館を結ぶネット美術館構想があり、年内に試験公開される方向だ。
ただ著作権については未定義な部分も多いと指摘。「コピーされてもいい程度の画質に落とすことでお茶を濁している。私はそれには反対で、高精細度のものをきちんと見てもらえるようにしたい。そのために、コンテンツにIDを付けて管理しようという研究も進めている」と述べた。さらに映像ポータルを通じて、さまざまなアーカイヴデータを検索できる「シームレスアーカイヴ」などの研究も進めているという。
今後の展開としては、高忠実度色再現技術や、Web上でも簡単に利用できる3D技術の開発などに加え、「触覚の実現や没入感の研究として触覚デバイスの利用や、裸眼で立体視できる技術の開発、音に関するアーカイヴ構築もも不可欠」と指摘する。また「高齢者・障害者向けでありつつ、健常者も同時に見られるコンテンツを開発していきたい。そのためには公的なコンテンツの評価手法の成立が必要である」と述べた。また今後、全国規模のアーカイブネットワークやサイトの整備や標準化にも注力する方向という。
 |
 |
| メディアプロデューサーの長屋龍人氏 | デジタルコンテンツ協会の工藤浩輔氏 |
京都では他の自治体に先駆けて、いち早くデジタルコンテンツに関する情報交流に取り組んできた面がある。今はその成果が、具体的な教育や、産業への展開として始まるところにあるといえる。京都からどんな新しいものが登場するのか、今後も注目していきたい。
(2003/1/30)
[Reported by 野々下裕子]