ニュース
NTT、OptQCと「光量子コンピュータ」実用化に向けた取り組みを発表、2030年までに100万量子ビットの実現目指す
2025年11月19日 12:45
NTT株式会社は11月18日、OptQC株式会社との連携により、光量子コンピュータの実用化に向けた取り組みを加速することを発表した。
OptQCは、東京大学・古澤明教授の古澤研究室が研究を進めてきた技術を基盤に設立した、同研究室発のスタートアップ企業だ。今回の提携により、両社では、2027年には国内トップレベルとなる1万量子ビット、2030年には世界トップレベルの100万量子ビットの光量子コンピュータの実現を目指す。また、100万量子ビットの実現にあわせて、ネットワークに最適化したラック型光量子コンピュータの開発も進めるという。
「100万量子ビットの実現が実用化の目安になる」
NTTの島田明社長 CEOは、「NTTが約60年間にわたって研究してきた世界トップレベルの光通信技術を量子分野に応用するとともに、OptQCが持つ光量子コンピュータ技術との連携を、より強固なものとし、スケーラブルで、信頼性の高い光量子コンピュータの実現と実用化を目指す。100万量子ビットの実現が実用化の目安になると見ており、NTTで光量子コンピュータに関わってきた数十人の研究者を、今回のプロジェクトに投入していくことになる」とした。
NTTでは、東京大学、理化学研究所とともに、光量子コンピュータの実現に向けた取り組みを進めており、現時点では、100量子ビットでの開発ができるという。また、すでに一部技術を量子コンピュータ分野に適用。光増幅技術を活用した量子光源により、従来の 1000倍以上もの高速な量子の生成を実現している。
OptQCの高瀬寛CEOは、「会社設立前を含めると、30年近く、光量子コンピュータの開発を行い、この技術を世界で初めて実証した実績がある。NTTとの連携によって、実機の研究開発のほか、社会実装やサプライチェーンの構築にも取り組む。世界トップの研究成果を生み出すとともに、社会実装にも狙いを置く。社会基盤として実装され、光量子コンピュータがない生活は考えられないという未来を目指す。IOWNによって、地球規模で結ばれた光量子コンピュータネットワークを実現したい」と抱負を述べた。
OptQCでは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」で1万量子ビット光量子コンピュータの開発を進めている。
光量子コンピュータは、光の特性を活用し、消費電力が低く、常温および常圧での動作が可能であることから、新しいアプローチとして注目を集めている。
これまでの量子コンピュータは、構造が複雑化しやすいという課題があるが、光を使うことで、シンプルに、大量の情報を一度に処理できる仕組みを構築。導入時には、大規模な設備投資が必要なく、コンパクトな量子コンピュータの設置を可能にしているのが特徴だ。
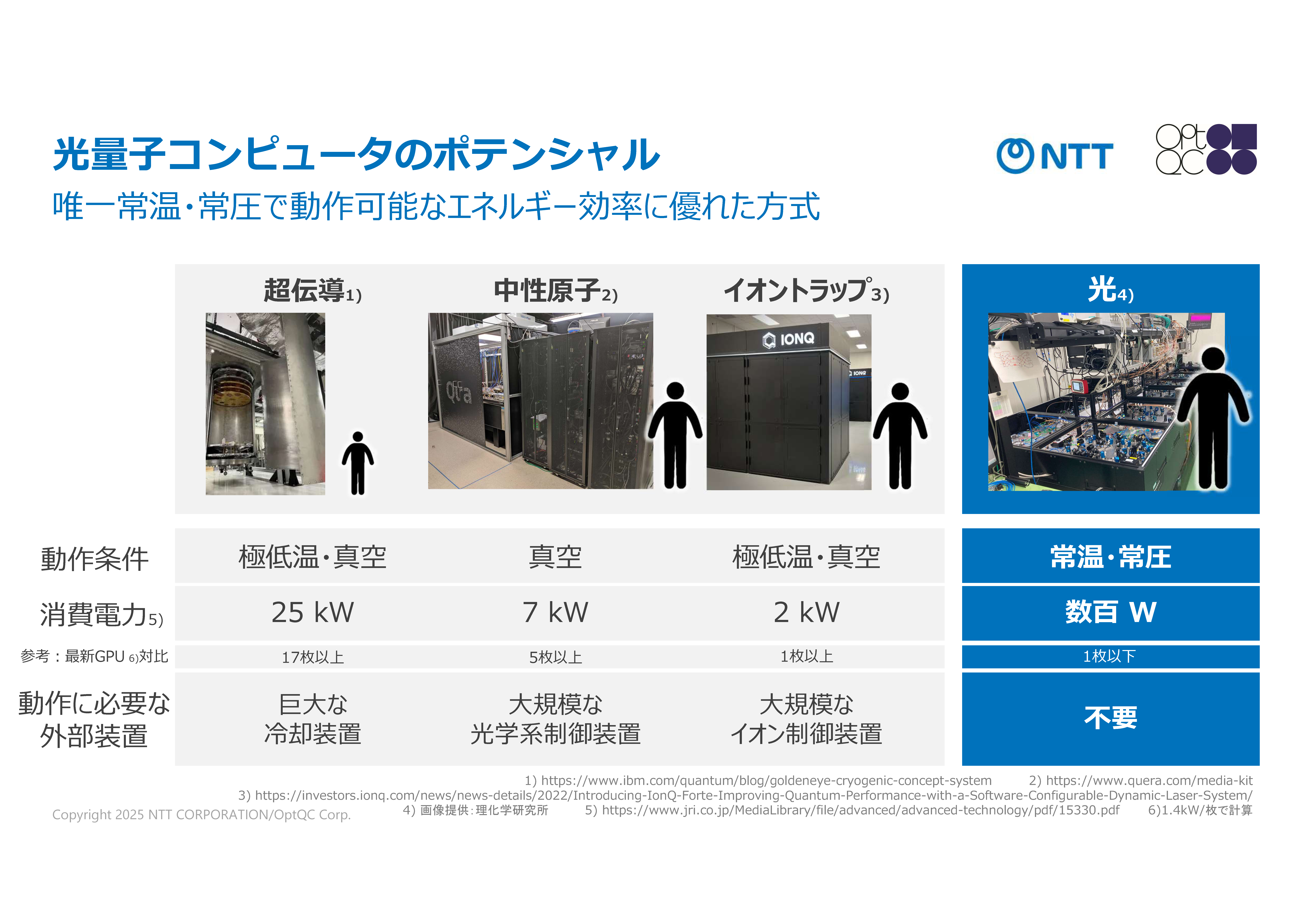
今回の提携では、量子コンピュータの実用化に不可欠な「スケーラビリティ」と「信頼性」を確保するために、NTTがIOWN構想のもとに推進してきた光増幅技術や光多重化技術などの光通信技術を、光量子コンピュータの開発に応用し、大規模で、複雑な社会課題の解決に貢献する光量子コンピュータの早期実用化を目指すとしている。
具体的には、「光量子コンピュータに活用可能な多重化技術や誤り訂正技術の創出」、「光量子コンピュータを用いたユースケース創出やアルゴリズム、ソフトウェアの開発」、「光量子コンピュータのサプライチェーン」、「光量子コンピュータやユースケースの社会実装」に取り組む。
NTTの島田社長 CEOは、「既存の量子コンピュータは、低温環境を維持するための冷却装置や、量子を操作するために大規模な制御装置が必要であるため、多くの電力を必要とする。だが、光量子コンピュータは、常温、常圧で動作するため、冷却機が不要になり、大規模な制御装置も不要である。消費電力は1桁以上の削減が可能であり、一般家電と同等の電力で動作させることができる。NTTがIOWNで培った光電融合技術を活用することで、抜本的な省エネ化を図れる。これは圧倒的な拡張性の高さにもつながる」と述べた。
両社は、今後5年間にわたり共同検討を実施し、初年度は、技術検討に着手するとともに、ユースケース創出に向けて、パートナーとの連携も推進。2年目には、開発環境を構築し、3年目にはユースケースの検証を実施する。さらに、2030年までに、100万量子ビットの光量子コンピュータを実現し、社会課題の解決に貢献するアプリケーションの開発を目指すという。
世界の食糧問題解決やパーソナライズ化した新薬開発も構想
量子ビットの拡大によるユースケースについても言及した。
1万量子ビットの実現によって、数日かかっていた計算が数分で完了するようになることから大規模な通信網、交通ネットワーク、エネルギーの配信などを、それぞれの状況に応じて社会規模で最適化。10万量子ビットになると、従来のコンピュータでは計算が不可能であった領域に進出でき、空気中の窒素から肥料を低エネルギーで生成し、食糧問題を解決できるようになるという。さらに、1億量子ビットの水準になると、80億人レベルでパーソナライズ化した新薬を作ることができるようになり、難易度の高い問題も解決できるようになるという。
「まずは、ニューラルネットワーク、AIの応用などで活用していく」(OptQCの高瀬CEO)という。
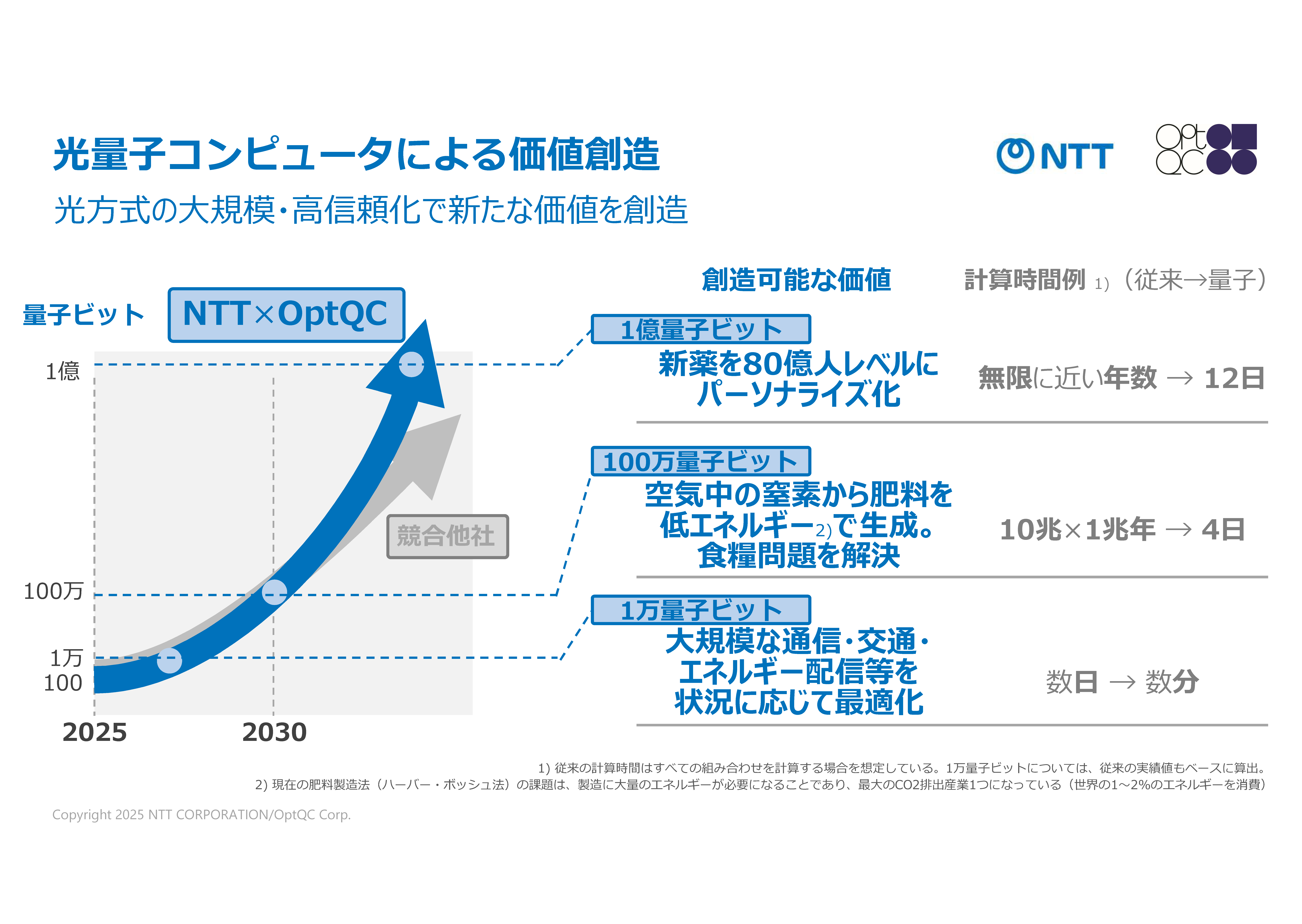
高瀬CEOは、学生時代から古澤研究室に在籍し、量子ビットの高レート生成手法の考案や、量子光パルスを自在に制御する手法の実証を行ってきた。東京大学大学院工学研究科において助教を務めていたが、2024年9月に退職し、古澤教授や、東京大学大学院工学系研究科のアサバナント・ワリット助教とともに、OptQCを創業し、CEOに就任した。
今後、100人規模に社員数を拡大し、150億円~300億円の資金調達を目指す。
2024年11月に開催された「NTT R&Dフォーラム 2024」で、光量子コンピュータに関するデモンストレーションを行っており、2024年11月には、シュレーディンガー猫状態の超高速生成に成功。2025年1月には、量子もつれの超高速生成に成功している。光量子コンピュータに関するデバイス技術や高信頼化システム技術は、2025年11月19日から、NTT武蔵野研究開発センタで開催する「NTT R&Dフォーラム 2025」で展示を行っている。

会見でビデオメッセージを寄せた東京大学・古澤明教授は、「NTTの光電融合技術を用いて、スーパーマシンを作ることになる。量子コンピュータは計算を速くするために生まれたのではなく、計算時のエネルギー消費を最小にすることが目的で生まれた。地球温暖化を止める最後の手段になるのが量子コンピュータである。そして、量産品の部品を使って作れるのが、光量子コンピュータの勝ち筋である。NTTはオーケストラのようなもので、各楽器の優秀な奏者がいる。私はそこでタクトを振ってみたいと思っている。Japan as No.1を取り返したい」と述べた。



