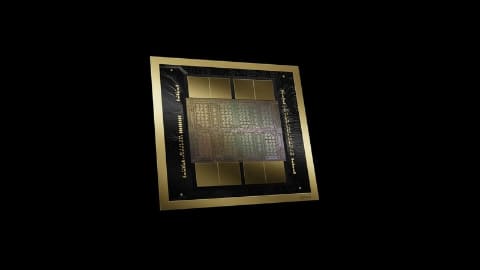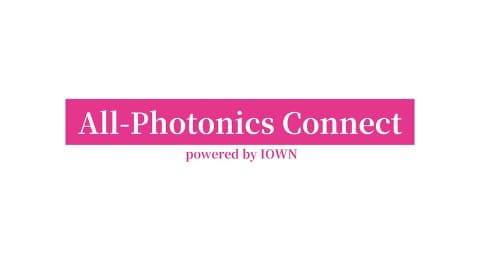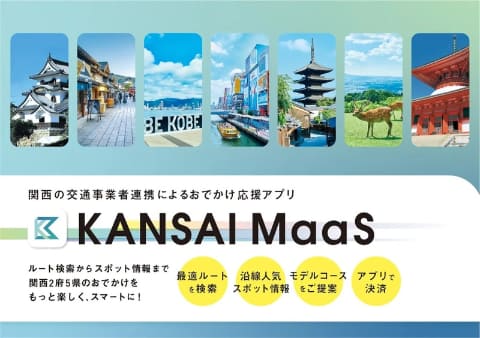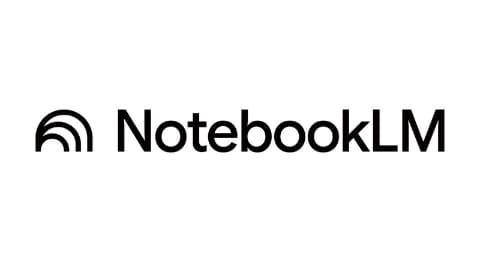ニュース
「MM総研大賞2025」、大賞はSkyDriveの「空飛ぶクルマ」〜ICT分野の発展を促す新プロダクトを表彰
“三次元空間”と“AIの急激な広がり”がキーワードに
2025年7月18日 13:00
ICT市場の調査などを行うMM総研は、「MM総研大賞2025」を発表した。
MM総研大賞は、ICT分野の市場、産業の発展を促すきっかけとなることを目的として、2004年に創設。優れたICT技術で積極的に新商品、新市場の開拓に取り組んでいる企業を表彰するもの。大賞は、SkyDriveの電動垂直離着陸機「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」が受賞した。また、「最優秀賞」には12分野の技術やサービスなどを選出したほか、「話題賞」も表彰した。
MM総研大賞の審査委員長を務めた村井純氏(慶應義塾大学特別特区特任教授)は、「テクノロジーが進歩し、それが広がり、人々に理解されることで、社会を変えていくことになる。MM総研大賞は、さまざまな視点から技術を捉えたものであり、審査委員会では、どんでん返しを含めたエキサイティングな議論が進められた」と報告。
「今回のMM総研大賞のキーワードのひとつが『三次元空間』である。エアモビリティであるSkyDriveの登場によって、日本での規制などが変化するという期待がある。また、海底から地上、空までを捉えた技術やサービスも最優秀賞を受賞している。もうひとつのキーワードが、『AIの急激な広がり』である。AIは、デジタルデータとコンピュテーション、ネットワークの組み合わせであり、最近では、AIをきっかけに、ワット・ビット連携(電力インフラと情報通信インフラの連携)の議論もはじまっている。私は、1980年代からインターネットへの取り組みを開始したが、多くの人がインターネットを利用しはじめたのが1995年である。それに比べるとAIの広がりはものすごく速い。いまは、AI前提社会となり、ハードウェアやサービス、ネットワークなどがそれに向けて進化し、デジタル社会のアーキテクチャを構成している。日本の国民全員が、それに気がついていることも驚きである。テクノロジーが全ての国民に理解されることは大変であるが、AIはそれを成し遂げている」と指摘した。
さらに、「日本から製品が生まれ、日本で製品が広がっていくことが大切である。そのためには、日本の市場で受け入れられる研究開発や製品開発を行い、それを品質に結びつけていかなくてはならない。日本の市場で受け入れられた技術や製品は、世界のさまざまな領域で貢献できるはずだ。これは日本の力である。日本の力を実現するのは企業であり、研究し、技術を作ることだが、それを使う国民の力も大きい。MM総研大賞は、日本の技術や製品に目を向けて、評価する努力をしている。これは大きな意義がある」と語った。
大賞の”空飛ぶクルマ”は「日本発の国産機としての将来性と革新性を評価」
MM総研大賞は、ICT市場の発展を促すことを目的に、2004年に創設した表彰制度で、今回で22回目となる。次世代のスマート社会を支える技術やサービスなどを表彰するスマートソリューション部門の「スマートソリューション部門最優秀賞」と、ICT分野に留まらず、社会的に大きな話題となった技術やサービスなどを「話題賞」として選んでいる。そのなかから、審査委員会が「スマート社会への貢献度」「今後のICT産業への影響度」などを選考基準に総合的に捉えて「大賞」を決定している。
選考においては、「認知度」「信頼性」「使いやすさ」「先進性/革新性」「独創性」「価格妥当性」「市場性」に加え、「基盤製品・サービスとしての可能性」などを評価基準としている。
MM総研の関口和一所長は、「22回目を迎えるMM総研大賞は、そのときどきの新しい技術やサービスを表彰し、日本のICT産業の振興に貢献することが主旨である。当初はPCやテレビ、デジカメ、スマホなどが中心だったが、ここ数年はソフトウェアやサービスなどに広がり、最近では生成AIやモビリティも対象になってきた」とし、「世の中で、最も注目を集めているAIブームはしばらく続くことになる。これからはAIを支えるための技術も必要になってくる。たとえば、通信技術はそのひとつであり、さまざまな技術が絡みあって、ICT産業が発展していくことになる。大賞となったSkyDriveの空飛ぶクルマは、新たなモビリティの姿を提案し、世界が大きく変わるものになる。それが、日本発の技術として開発され、世界に届けていくことになる」と評した。
MM総研大賞を受賞したSkyDriveの電動垂直離着陸機「SKYDRIVE(SD-05型)」は、ヘリコプターと比べて静粛性や軽量化による利便性を持つほか、機体構造がシンプルであるため、経済性における効果も期待されている。大阪・関西万博では、「空飛ぶクルマ」として、公開デモフライトを実施し、新たなモビリティとして注目が集まっている。
世界でeVTOL(電動垂直離着陸機)の開発競争が激しくなるなか、日本発の国産機としての将来性と革新性を評価したという。スマートソリューション部門の次世代モビリティ分野の「最優秀賞」も受賞した。
SkyDriveの福澤知浩社長は、「SkyDrive は、『100年に一度のモビリティ革命を牽引する』をミッションに掲げ、日常の移動に空を活用する未来を目指して、2018年に設立した企業である。3人乗りのSD-05型は、100%電気で駆動し、ヘリコプターよりもコンパクトであり、軽量化、静粛性も持ち、実用的に空を移動できる。実用化まで、さまざまな課題はあるが、多くのパートナー企業などとの連携や応援を得て、日常的に空を利用したり、緊急時に空を利用したりすることで、快適な未来と楽しい移動を実現していく。日本だけでなく、グローバルでの移動の課題解決にも貢献したい。MM総研大賞の名前に恥じないように、日本から新たなイノベーションを海外に展開していきたい」と語った。
12分野における最優秀賞として13社を選出
MM総研大賞では、スマートソリューション部門として、AI、半導体、光通信サービス、光通信インフラ、非地上通信、衛星データ、地域モビリティ、次世代モビリティ、DX支援、DXソリューション、スマートデバイス、次世代ロボットの12分野における最優秀賞として13社を選出した。最優秀賞および話題賞は以下の通り。
AI分野 最優秀賞
日本IBM「watsonx」
企業向けのAIプラットフォーム「watsonx」は、独自の小規模かつオープンな言語モデルである「Granite」をはじめ、複数モデルから選択ができるのが特徴。ビジネス変革やコード生成といったITモダナイゼーションおよび変革において貢献する点を評価した。
ソフトバンクグループ 「Stargate Project」「クリスタル・インテリジェンス」など
AIインフラを構築する「Stargate Project」や、企業用最先端AIである「クリスタル・インテリジェンス」を発表するなど、AIの社会実装や、AGIおよびASIの実現に向けたグループ総力での取り組みを評価した。
半導体分野 最優秀賞
NVIDIA 「NVIDIA Blackwell」
生成AIとアクセラレーテッドコンピューティングの新時代を支えるGPUアーキテクチャとして、高い処理性能を実現。AIの大規模な学習から推論までを支える製品力と将来性を評価した。
光通信サービス分野 最優秀賞
NTT東日本/NTT西日本 「All-Photonics Connect powered by IOWN」
「All-Photonics Connect powered by IOWN」では、ユーザー拠点間の帯域保証型通信としては世界高水準となる最大800Gbpsの実現に加え、高速、大容量通信、低遅延を特徴としており、データセンター間接続や通信キャリアのバックボーン、遠隔医療での活用などの将来性も評価した。
光通信インフラ分野 最優秀賞
NEC 「光海底ケーブル事業」
国際的な通信で重要な役割を果たす光海底ケーブルで世界トップクラスの実績を誇り、デジタルインフラの構築を、設計、製造から工事までをトータルソリューションとして提供し、国際社会の発展を支える点を評価したという。
非地上通信分野 最優秀賞
KDDI 「au Starlink Direct」
スマートフォンが通信衛星と直接つながり、空が見えればどこでもテキストメッセージの送受信が可能となるサービスであり、通信インフラの整備が困難な場所や災害時の通信手段として、その有用性や将来性を評価した。
衛星データ分野 最優秀賞
NTTデータ/Marble Visions 「Marble Visions」
衛星データから3D地図を作成する技術である「AW3D」を活用して、衛星画像の撮像から解析までをワンストップで提供。デジタルツイン構築を支援するMarble Visionsの成長性も評価した。
地域モビリティ分野 最優秀賞
関西MaaS協議会 「KANSAI MaaS」
関西に路線を持つ鉄道会社7社が共同で提供するスマートフォン向けアプリで、日本初の鉄道事業者の連携による広域型MaaSとして注目されている。大阪・関西万博の観光需要促進にも貢献しているという。
次世代モビリティ分野 最優秀賞
SkyDrive 「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」
MM総研大賞。前述のとおり。
DX支援分野 最優秀賞
NEC 「BluStellar」
NECの価値創造モデルであるBluStellarは、先進的な知見と最先端テクノロジーによってビジネスモデルを変革し、社会課題と顧客の経営課題を解決する。NECが持つSIの豊富な知見と実績をもとに、「型化」したサービスを、安心に最速で提供する。生成AIや顔認証など独自技術を含む点を評価した。
DXソリューション分野 最優秀賞
三菱商事/KDDI/ローソン 「Real×Tech Convenience」
未来のコンビニと位置づける「Real×Tech Convenience」は、通信とデジタル技術を基盤に、スマホレジやAIサイネージ、リモート接客など、生活に根ざした技術の社会実装に取り組んでおり、ブランド力や事業基盤、Ponta経済圏を生かした拡張性と社会的インパクトを評価した。
スマートデバイス分野 最優秀賞
小米技術日本(シャオミ・ジャパン) 「スマートフォンなどの製品群」
小米技術日本は、ハードウェアの利益率を、永久に5%以下に抑えるとし、コストパフォーマンスの高いスマートフォンなどの製品群を投入。日本では、2019年にスマホ市場に参入し、2024年以降は家電製品や日用品にもラインアップを拡充し、さまざまな製品を展開している点を評価した。
次世代ロボット分野 最優秀賞
ソラリス 「Sooha」
Soohaは、世界初の空気圧人工筋肉を利用したミミズ型管内走行ロボットであり、ミミズのように伸縮動作を繰り返しながら前進できる。配管内での点検や清掃作業が可能であり、近年の道路陥没件数の増加など、喫緊となる社会インフラの老朽化対策にも貢献できる。細管内など、人や他のロボットが入れず維持管理が難しい場所のインフラ整備で活躍が期待される。
話題賞
グーグル合同会社 「NotebookLM」
NotebookLMは、リサーチや執筆のためのAIアシスタントツールと位置づけられ、複雑な情報を整理し、新たな洞察を生むことができるという。学生の研究論文作成やビジネスパーソンの市場分析、クリエーターのアイデア発想に加えて、教育現場などにも応用できる有用性を評価した。
なお、審査委員は以下の通り。
- 審査委員長
慶應義塾大学特別特区特任教授 村井純氏 - 審査委員
一般社団法人モビリティ・イノベーション・アライアンス理事長 天野肇氏
九州大学大学院経済学研究院教授 篠﨑彰彦氏
NPO法人CANVAS理事長 石戸奈々子氏
フリージャーナリスト 西田宗千佳氏
MM総研 研究課長 高橋樹生氏